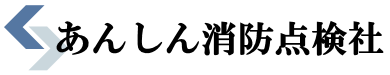���h�ݔ��̓_��������悤�ɏ��h������w���������A�ǂ���������́H

���܂������������B���Ђł͎����������ɂ����ď��Ί�P�{����ł����h�ݔ��̓_�����s�Ȃ��A���h�p�ݔ����_�����ʕ��y�ъe���h�ݔ����Ƃ̓_���[�i�܂��͏��h�p�ݔ����_�����ʑ����\�j���쐬�������܂��B�����ς肾���ł��A���C�y�ɂ����k���������B
���h�ݔ��_���F�@��_���͂U�����ɂP��ȏ�A�����_���͂P�N�ɂP��ȏ���{����`��������܂��B���̓s�x���h�p�ݔ����_�����ʕ��y�ъe���h�ݔ����Ƃ̓_���[�i�܂��͓_�����ʑ����\�j���쐬���܂��B���h�@�ււ͓̕���h�ΑΏە����P�N�ɂP��A�����h�ΑΏە��͂R�N�ɂP��ƂȂ�܂��B
������h�_����
TEL�O�X�X�|�Q�O�W�|�V�P�S�P
���������̏��h�ݔ��_���́A���C�y�ɂ��₢���킹�������B
����h�ݔ��_���̎�ȑΉ��G���A�E������������
���������i�������s,�����s,���ǎs,�F������s,���������ؖ�s,���u�s,�w�h�s,�삳�s,����s,���v���s,���̑��j
���h�ݔ��_���̗����́H
���h�ݔ��_���̗����́A���h�ݔ��̎�ށA���ʁA�����̋K�́A���ɂ���ėl�X�ł��B���Ђł́A���f�����Đݒu����Ă�����h�ݔ������n�ɂĊm�F�����Ă�����������ŁA���ς���s�Ȃ��Ă���܂��B���ς�͖����ł��̂ŁA���C�y�ɂ��₢���킹���������B
�������̏��h�ݔ��_���͂��C�y�ɂ��₢���킹���������I
�����������h�ݔ����S��������X
���h�ݔ��Ƒ����ی������X
������h�_����
TEL�O�X�X�|�Q�O�W�|�V�P�S�P
�����@�u�@�{�@�Ё@�@��899-2505 �����������u�s�ɏW�@�������q74
�����h�ݔ��ێ�����@��897-1123 ���������삳�s�����c����2066-121
����h�ݔ��_���̎�ȑΉ��G���A�E������������
���������i�������s,�����s,���ǎs,�F������s,���������ؖ�s,���u�s,�w�h�s,�삳�s,����s,���v���s,���̑��j
���h�ݔ��_���ɂ��āi�����������j
 |
�������Е�m�ݔ��i��M�@�j
�����Е�m�ݔ��̑���Ղł����M�@�̏��h�_���̗l�q�ł��B(�ʐ^�͎���������)�Ђ������������m���m�点�Ă���鎩���Е�m�ݔ��͏��h�ݔ��̒��ł����ɏd�v�Ȑݔ��Ƃ����܂��B�����Е�m�ݔ��̎�M�@�̑�����@�A�菇���͋@��ɂ���ĈقȂ�܂��B�Ў����͌�쓮���̍ۂ̎�M�@�̊m�F�̎d���⑀����@�ȂǁA���Ə��̐E���̊F�l���n�m����邱�Ƃ������߂��܂��B
�܂������Е�m�ݔ��́A�����I�ɏ��h���ɉЂ̔�����ʕ�ݔ��ł͂���܂���B��{�I�Ɏ����Е�m�ݔ��́A�Ђ̔����������������m���A�������ɂ���l�ɒm�点��̂���ȖړI�ł��B
���x���������ۂ́A�����Е�m�ݔ��̎�M�@�łǂ̏ꏊ���Ђ����m�����ꏊ�����m�F���Č�����m�F����K�v������܂��B�����Ђł���A�P�P�X�Ԃŏ��h���ɉЂ̔�����m�点��K�v������܂��B�A���A�x����Г��Ɏ����I�ɒʕ����悤�Ɍ_�Ă���ꍇ��A���h���Ɏ����I�ɉЂ̔�����m�点��Вʕu�ƘA�����Ă���ꍇ������܂��̂ŁA���ΌP�������s�Ȃ����ʼnЂ̔�����z�肵�ď��h�ݔ����ǂ̂悤�ɋ@�\����̂��A�c�����Ă������Ƃ���ɂȂ�܂��B |
|---|---|
|
|
�������Е�m�ݔ��_���i���m��j
�������ɂ�芴�m��ɔM�ĂāA����ɍ쓮���邩�������s�Ȃ��܂��B(�ʐ^�͎���������)���m��ɂ́A�M�����m������́A�������m������́A�������m������̓��A�l�X�Ȏ�ނ�����A�����̏⍂�����ɂ���ėp���邱�Ƃ̂ł��銴�m�킪���߂��Ă��܂��B |
|
|
�������Е�m�ݔ��_���i�����m�튴�x�����j
���h�ݔ��_���̒��̑����_���̍ہA�����m��̊��x�𑪒肵�Ă��܂��B(�ʐ^�͎���������)�`���ł������܂������A�������̓��L�̎��ۂƂ��č����̉ΎR�D�̉e���ʼn����m�킪��쓮���邱�Ƃ�����܂��B�O�C�ɐڂ���ꏊ�╗�ʼnΎR�D�����ꍞ�ނ悤�ȏꏊ�ɉ����m�킪�ݒu����Ă���ꍇ�͒��ӂ��K�v�ł��B |
|
|
�����Ί�_���i�O�ϓ_���j(�ʐ^�͎���������)
���Ί�͏��h�ݔ��̒��ł��A�ł���ʓI�Ȃ��̂Ƃ����܂��B��ʉƒ�ɂ͐ݒu�͋`���ł͂���܂��A�����̉Ђɂ͑傫�Ȍ��ʂ�����܂��̂łP�ƂɂP�{�͐ݒu����邱�Ƃ������߂��܂��B
�������V��ɂ܂œ͂��悤�ȉ��ɂȂ��Ă��܂����ꍇ�́A���͂��Ȃ����Ȃ�܂��B�܂��������Ζ�܂̏ꍇ�A���̉e�������Ȃ�܂��̂ŁA������������ˋ����ɂ����ӂ��K�v�ł��B
�g�p���@�͓�����̂ł͂���܂��A�Ђ̍ۍQ�ĂĂ��܂��ƓK�Ɏg�p�ł��Ȃ��Ȃ邩������܂���B���Ə���n��ōs������h�P���ɎQ������āA�g�p���@���悭�m���Ă����̂͑�ł��B���Ђł��A������ �����ɂ����āA�n��̊F���܂⎖�Ə��̊F�l�̏��ΌP���ɎQ�������Ă��������A�g�p���@���������������Ă��������Ă���܂��B
���������Ί�ɂ��ẮA���H�i�T�r���j������Ɣj�邱�Ƃ������ϊ댯�ł��B����x�A���m�F���I�ŋ߂ł͂����S�Ȓ~�������Ί킪�嗬�ɂȂ��Ă��܂��B�~�������Ί�ɂ́A���̓Q�[�W�����Ă���A����I�ɏ��Ί�����̈��͂��K����ɂ��邩�̓_������ł��B
�܂����Ђ́A���Ί탊�T�C�N���̓��葋���ƂȂ��Ă���܂��B�p���ɂ��ẮA���C�y�ɂ����k���������B�i�ڂ����́A���Ί탊�T�C�N�����i�Z���^�[�̃T�C�g���������������B�j���Ί�ɂ��ẮA���Ί�̃y�[�W���������������B
|
|
|
�����Ί�_���i�����y�ы@�\�_���j(�ʐ^�͎���������)
�����g�p����Ă��镲���`�a�b��܂́A�����_�A�����j�E�����听���Ƃ��Ă��܂��B
�����Ζ�܂̋l�ւ��́A���h�ݔ��m�i����U�ށj�łȂ���s�����Ƃ��ł��܂���B������o���Ă��܂����ۂɂ͏��h�ݔ��m�̂�����h�ݔ��Ǝ҂ɖ�܋l�ւ����˗����ĉ������B(���h���ł́A�l�ւ��͍s�Ȃ��Ă��܂���B) |
|
|
���Вʕu�_��(�ʐ^�͎���������)
���h�ݔ��̈�A�Вʕu�͉Ђ̔��������h���֒ʕ�@��ł��B���̎ʐ^�͉Вʕu���g���ď��h���֒ʕĂ���Ƃ���ł��B�����Е�m�ݔ��ƘA�����ĉД������Ɏ����ŏ��h���֒ʕ��ݒ�ƁA�E�����蓮�Œʕ�K�v�̂���ꍇ�Ƃ���܂��̂ŁA�ЌP�����ŏn�m����邱�Ƃ������߂��܂��B |
|
|
���U�����_��(�ʐ^�͎���������)
���h�ݔ��̒��̔��ݔ��Ɋ܂܂��U�����B�Ђɂ���d���≌�̒��ŁA���ꏊ�ɑ������S�ɓ����邽�߂ɗU�����͏d�v�ł��B���݂�LED�U�������嗬�ł��̂ŁA�u�������P�A�Q�N���x���ƂɌ��������Ԃ��Ȃ��A�Ǘ������₷���Ȃ��Ă��܂��B���h�_���ł́A�_���̊m�F��o�b�e���[�̎����������{���܂��B |
|
|
���������ΐ�ݔ��_��
�d���@�E�|���v���̓_���B(�ʐ^�͎���������)
���h�ݔ��̒��̏��ΐݔ��ɕ��ނ���鉮�����ΐ�ݔ��́A�Ў��̏��ɑ傫�ȈЗ͂�������h�ݔ��ł����A�g�p���@�����Ɛ����Ńz�[�X���\��傫�ȉ���ɂȂ���댯������܂��B�P�l�ő���ł�����̂ƂQ�l�ő��삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ȃǂ�����܂��̂ŁA���ΌP�����Ŏg�p���@���n�m�����悤�����߂��܂��B |
|
|
���������ΐ�ݔ��_��
�������ΐ�ݔ��̕����̗l�q�ł��B(�ʐ^�͎���������)���h�ݔ��_���̍ۂ́A���������𑪒肵�܂��B���g�p�̍ۂ́A���ΐ��i�[���Ɏ�舵�����@���L�ڂ��Ă���܂��̂ŁA�m�F�̏�g�p���Ă��������B���Ȃ�̐������|����ꍇ������܂��̂ŁA�����̍ۂ̃o���u����͐T�d�ɂ���悤�ɂ��Ă��������B |
|
|
���������ΐ�ݔ��_��
�������ΐ�p���h�z�[�X�̑ψ������̗l�q�ł��B(�ʐ^�͎���������) |